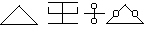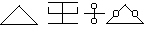うつろ舟の蛮女−「兎園小説」 巻二十
享和三年癸亥の春二月廿二日午のときばかりに、当時寄合席小笠原越中守(高四千石)知行所常陸国はらやどりといふ浜にて、沖のかたに舟の如きもの遙かに見えしかば、浦人等小船あまた漕ぎ出しつつ、遂に浜辺にひきつけてよく見るに、その舟の形、たとへば香盒のごとくしてまろく、長さ三間あまり、上は硝子にしてチャンをもて塗りつめ、底は鉄の板がねを段々のごとく張りたり。海巌にあたるとも打ち砕かれざる為なるべし。上より内の透き通りて隠れなきを、みな立ち寄りて見てけるに、そのかたち異様なるひとりの婦人ぞいたりける。
そが眉と髪の毛赤かるに、その顔も桃色にて、頭髪は仮髪なるか、白く長くして背に垂れたり。
(頭書、解按ずるに、二露西亜一見録人物の条下に云、世の衣服が筒袖にて腰より上を、細く仕立て云々、また髪の毛は、白き粉を塗りかけ結び申候云々、これによりて見るときは、この蛮女の頭髻の白きも白き粉を塗りたるならん。露西亜属国の婦人にやありけんか。なほ考ふべし。)
そは獣の毛か。より毛か。これをしるものあることなし。遂に言葉の通ぜねば、いづこのものと問ふよしあらず。この蛮女二尺四方の箱をもてり。特に愛するものとおぼしく、しばらくもはなさずして、人をしもちかづけず。その船中にあるものを、これかれと検せしに、水二升許小瓶に入れてあり。
(一本に、二升を二斗に作り、小瓶を小船に作れり。いまだいづれかこれを知らず。)
敷物二枚あり。菓子やうのものあり。又肉を練りたる如き食物あり。
浦人等うちつどいて評議するを、のどかに見つつゑめるのみ。故老の云、これは蛮国の王の女の他へ嫁したるが、密夫ありてその事あらはれ、その密夫は刑せられしを、さすがに王の娘なれば、殺すに忍びずして、虚舟(うつろぶね)に乗せて流しつつ、生死を天に任せしものか。しからば其箱の中なるは、密夫の首にやあらずらん。むかしもかかる蛮女のうつろ舟に乗せられたるが、近き浜辺に漂着せしことありけり。その船中には、まな板のごときものに載せたる人の首の、なまなましきがありけるそし、口碑に伝ふるを合わせ考ふれば、件の箱の中なるも、さる類のもななるべし。されば、蛮女がいとおしみて身をはなさざるなめりといひしとぞ。かの事、官府へ聞こえあげ奉りては、雑費も大かたならぬに、かかるものをば付き流したる先例もあればとぞ、又もとのごとく船に乗せて、沖へ引き出しつつ推し流したりとなん。もし人仁の心もてせば、かくまでにはあるまじきを、そはその蛮女の不幸なるべし。又その船の中に、※(脚注)等の蛮字の多くありしといふによりて、あとに思ふに、ちかきころ浦賀の沖にかかりたるイギリス船にも、これらの蛮字ありけり。もしくはベンガラ、もしくはアメリカなどの蛮王の女なりけんか。これも亦知るべからず。
※船中の蛮字