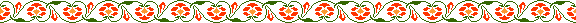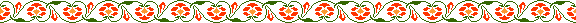
|
④_蕪村妖怪絵巻(与謝蕪村) |
 遠州の夜なきばば.jpg |
 横手のうぶめ |
 鎌倉若八幡銀杏の化物 |
 京都帷子が辻のぬっぽり坊主 |
 榊原家の化け猫 |
 山城の真桑瓜の化物 |
 木津の西瓜の化物 |
 林一角坊の前に現れた赤子の怪 |
|
『蕪村妖怪絵巻』(ぶそんようかいえまき)は、 江戸時代中期の俳人・画家である与謝蕪村による日本の妖怪絵巻。 蕪村が寄寓していた京都府宮津市の見性寺の欄間に 張られていたものと伝えられており、 そのことから、宝暦4年から7年(1754年-1757年)にかけて 蕪村が丹後国宮津(現・京都府宮津市)で 絵を修行していた間に描かれたものと推察されている。 全8点の妖怪が描かれているが、 単に妖怪を紹介しているのみのものから、 妖怪の物語を綴ったものまであり、 蕪村が日本各地を旅していた時期に、 あちこちで伝え聞いた妖怪譚を描いたものと考えられている。 俳画に長ける蕪村の妖怪画は、 妖怪として真に迫ったものというよりはむしろ、 漫画に近いユニークな画風が特徴である。 日本の中世における妖怪画は、 恐怖と災厄の象徴としての妖怪を描いたものがほとんどだが、 この蕪村を含む江戸時代の妖怪画は、 滑稽なものや親しみのあるものとして描かれるものが多く、 妖怪をフィクションとして楽しもうとする娯楽性が見て取れ、 現代の妖怪漫画にも通じているとの見方もある。 原典の所属先は不明だが、 昭和3年(1928年)に北田紫水文庫から刊行された復刻版によって 内容を知ることができる。 |
|
戻る |